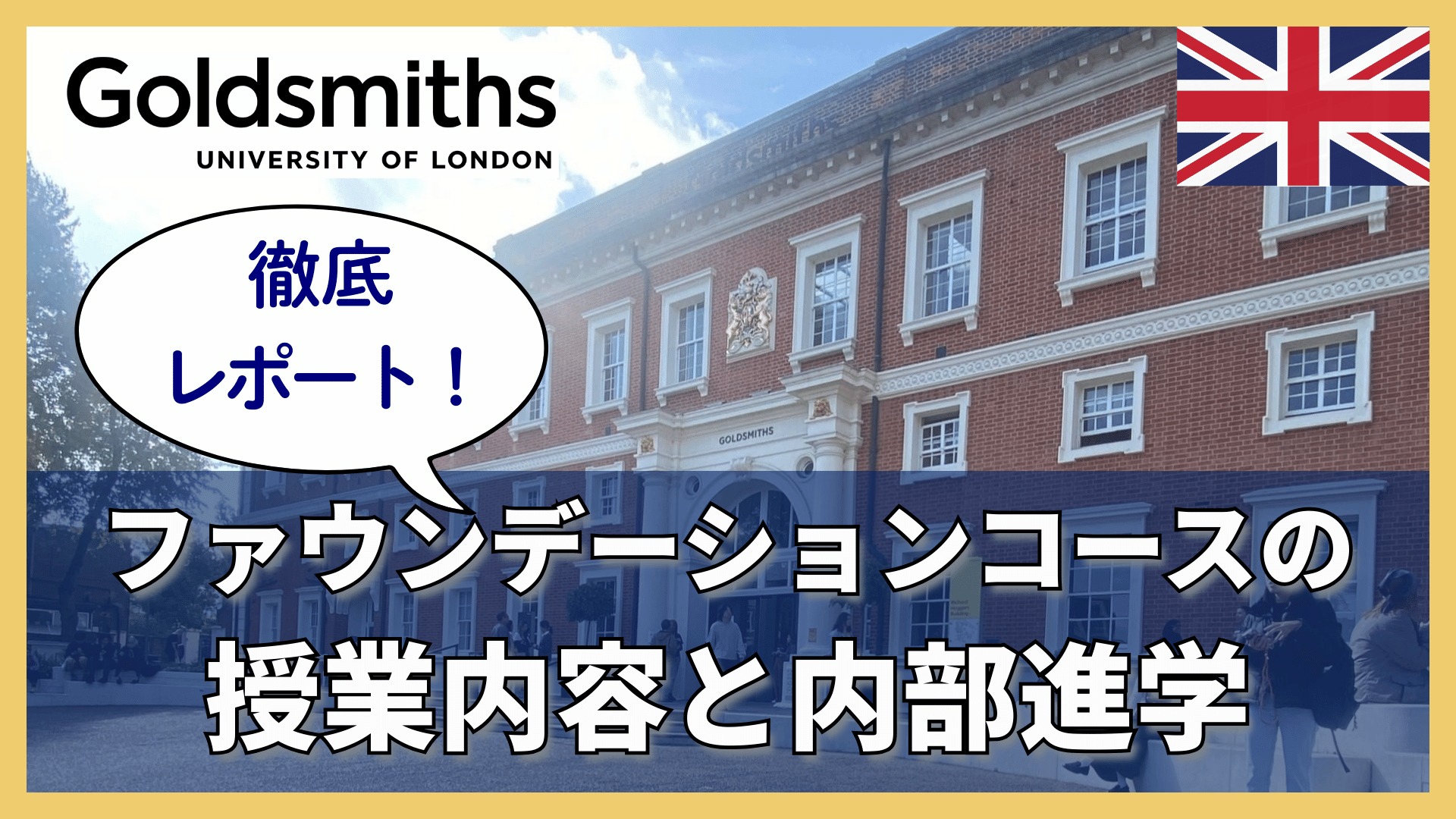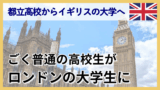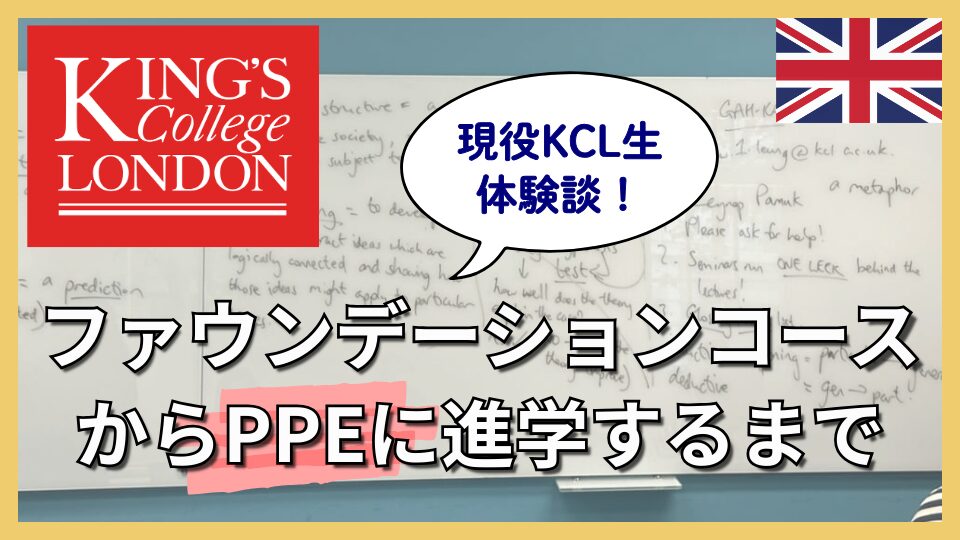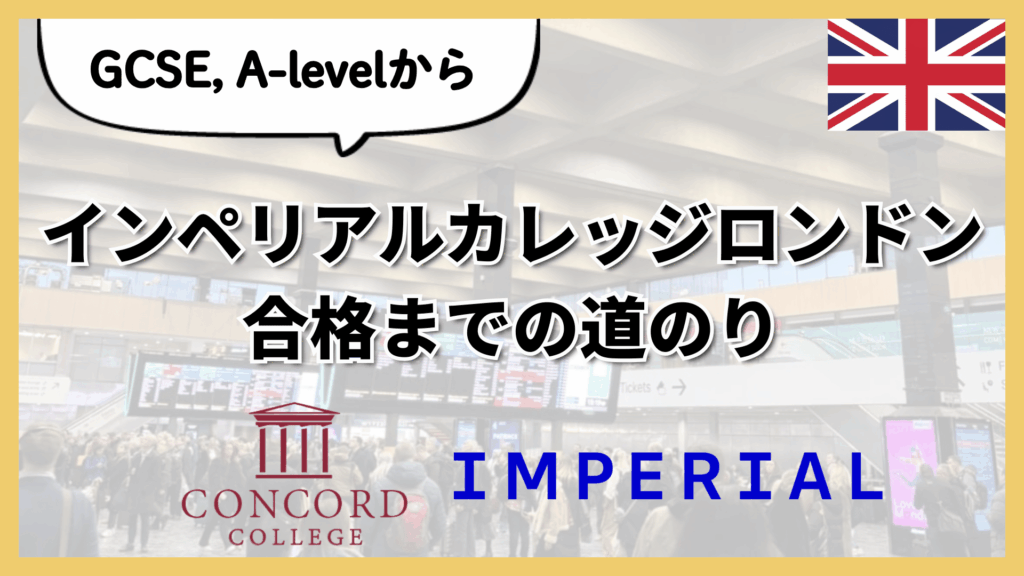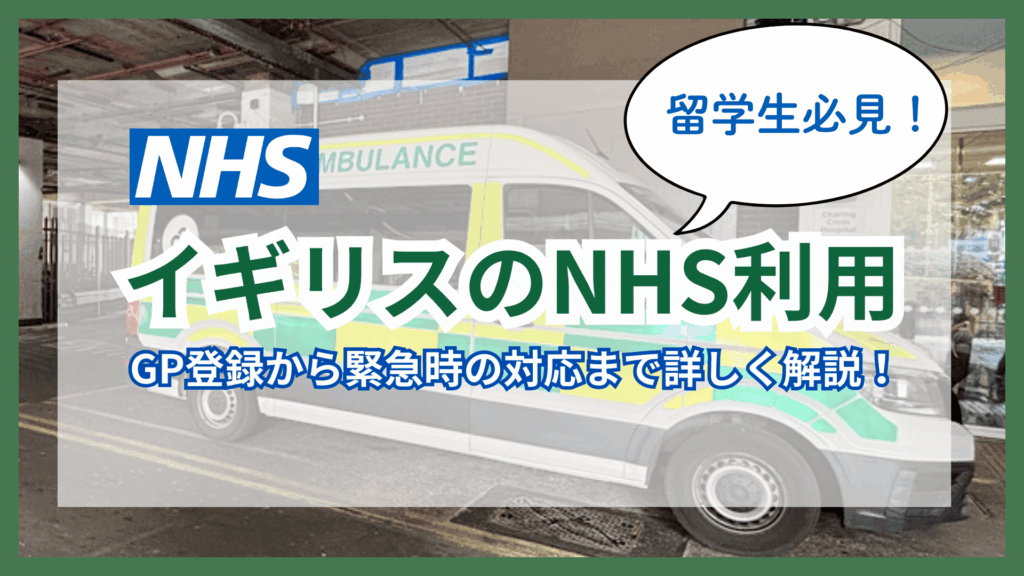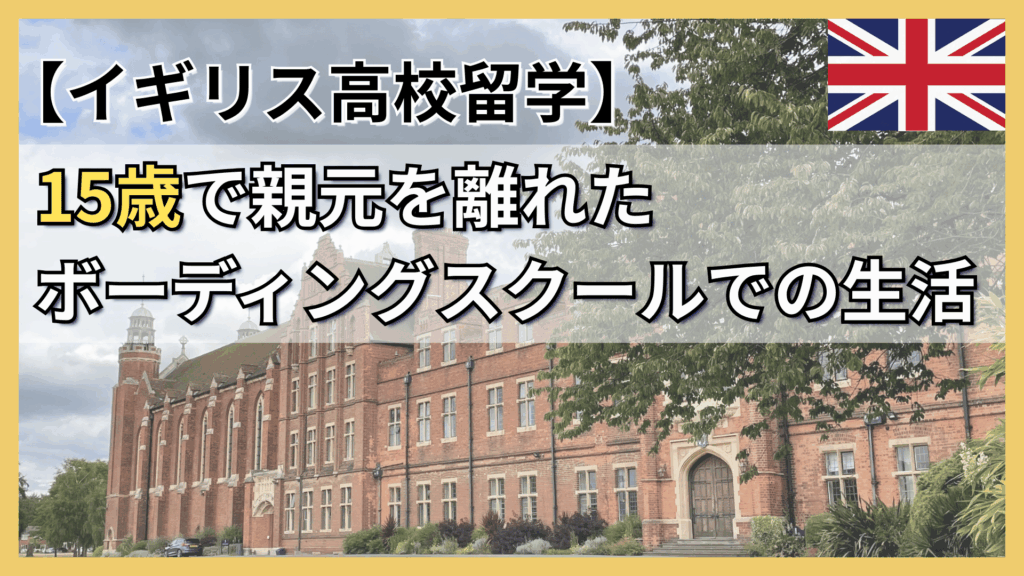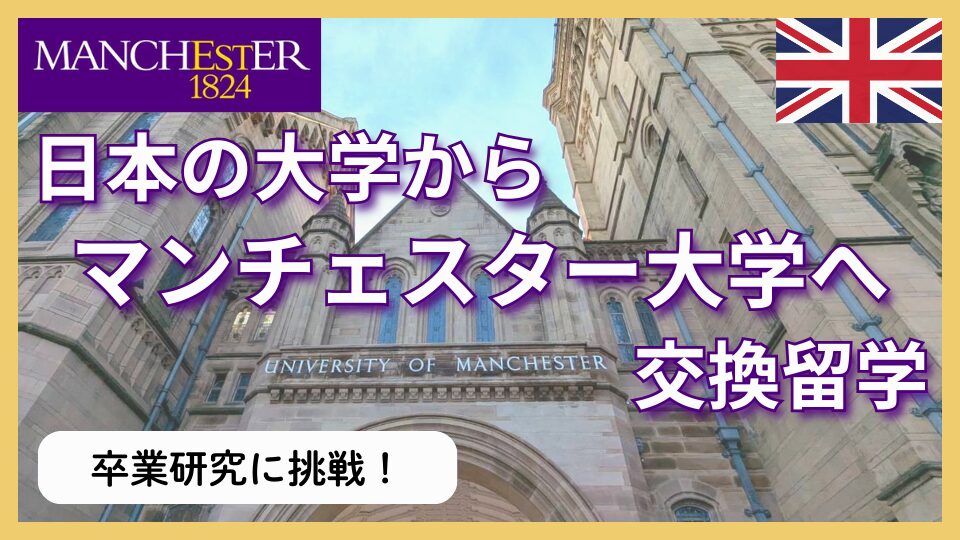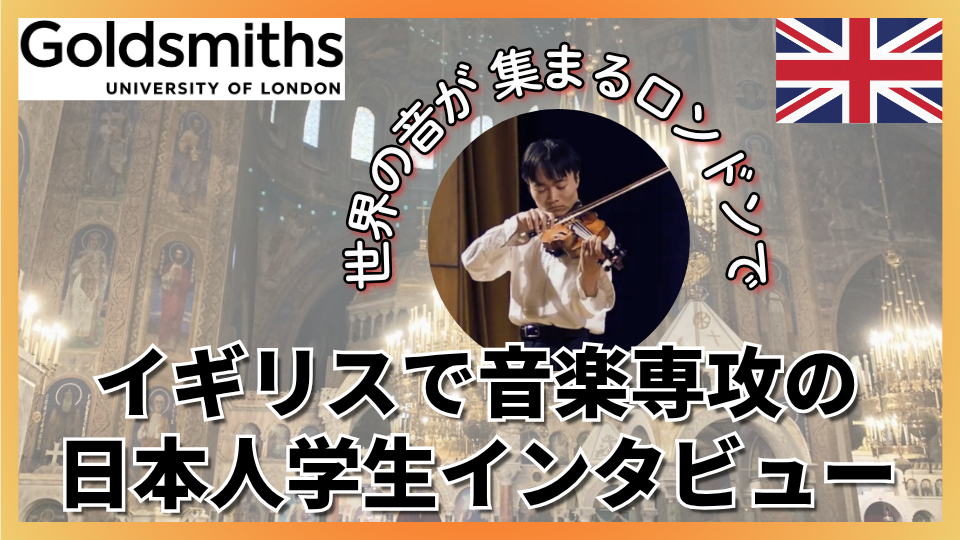こんにちは! Goldsmiths, University of London(ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ)でメディアを勉強しているKotokoです。
今回は日本の高校卒業後に受講したファウンデーションコースでの1年間をご紹介します。どんなことを学んだのか、英語力がどれくらい伸びたのかなど、リアルな体験をお伝えします!
※私が経験したのはGoldsmithsのファウンデーションコースなので、他の大学とは違う部分もあるかもしれません。あくまで1つの体験談として読んでもらえたらと思います!
前回の記事では、「ごく普通の高校生だった私がイギリスの大学に合格するまでの道のり」について書きました。まだ読んでいない方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね!
ファウンデーションコースとは?
ファウンデーションコースは、主に留学生を対象とした、イギリスの大学に進学するための準備プログラムです。英語力や学問的な基礎を1年間かけて学び、大学の授業についていける力を養います。
イギリスの大学は通常、A-levelやIB(国際バカロレア)などの国際的な資格を入学基準としています。日本の高校卒業資格だけではそのまま入学できないです。そのため、多くの日本人学生はこのコースを経て進学します。
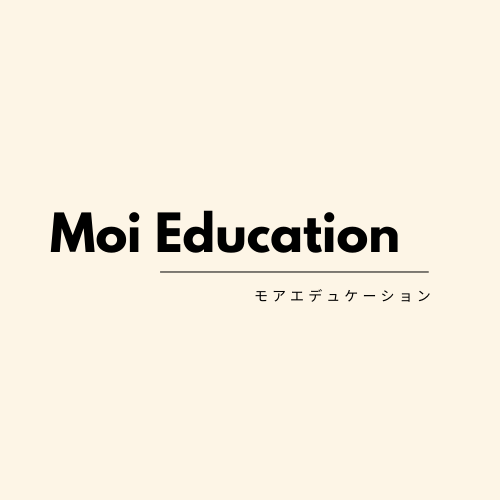
ロンドン大学ゴールドスミスカレッジのファウンデーションコース
キャンパスはロンドン郊外
私が受講したのは、ロンドン南東部にあるGoldsmithsが提供しているファウンデーションコースです。
キャンパスはOverground(地上を走る鉄道)のNew Cross駅から歩いてすぐです。ロンドン中心部からは電車で30分ほどかかります。近くにはRoyal Observatory(グリニッジ天文台)で有名なGreenwich Park(グリニッジ・パーク)があります。
住宅街に位置しているため、中心地ほど便利なわけではありません。その反面、落ち着いたローカルな雰囲気の中で大学生活を送ることができます。
ただし、夜は少し治安が悪いという声もあり、注意が必要なエリアだと感じます。

キャンパスの雰囲気と施設
Goldsmithsは、アート、デザイン、メディア、カルチャーなどクリエイティブな分野に強いことで知られています。それを体現しているように、キャンパス全体に自由な表現があふれています。壁にはアート作品が展示されていたり、学生によるエキシビションが定期的に開催されたりしています。
キャンパスの中心にはRichard Hoggart Buildingというメインの建物があります。それを囲むようにアート系やメディア系など、専門分野ごとに建物が分かれています。
私が所属しているメディア学科にはラジオ制作のためのブースなどがあり、技術的なスキルを学ぶ環境がしっかり整っています。

Richard Hoggart Buildingの隣には24時間利用可能な図書館があります。豊富な蔵書はもちろん、パソコンの貸し出しや印刷機、会議室なども充実しています。このように、学習をサポートする設備には困りません。
また、キャンパスの中央には芝生が広がっています。春から夏にかけてそこで昼食をとったり、お昼寝したりと、のんびりと過ごす学生が多いです。
キャンパス内にはいくつかのカフェがあります。中でもGoldsmiths Students’ Union※(学生組合)が運営するカフェは、他のカフェよりも価格が手頃です。飲み物や軽食も美味しく、私のおすすめスポットです。
※Students’ Unionは学生の声を大学に届けたり、クラブ活動やイベントの企画・運営、サポートを行う組織です。
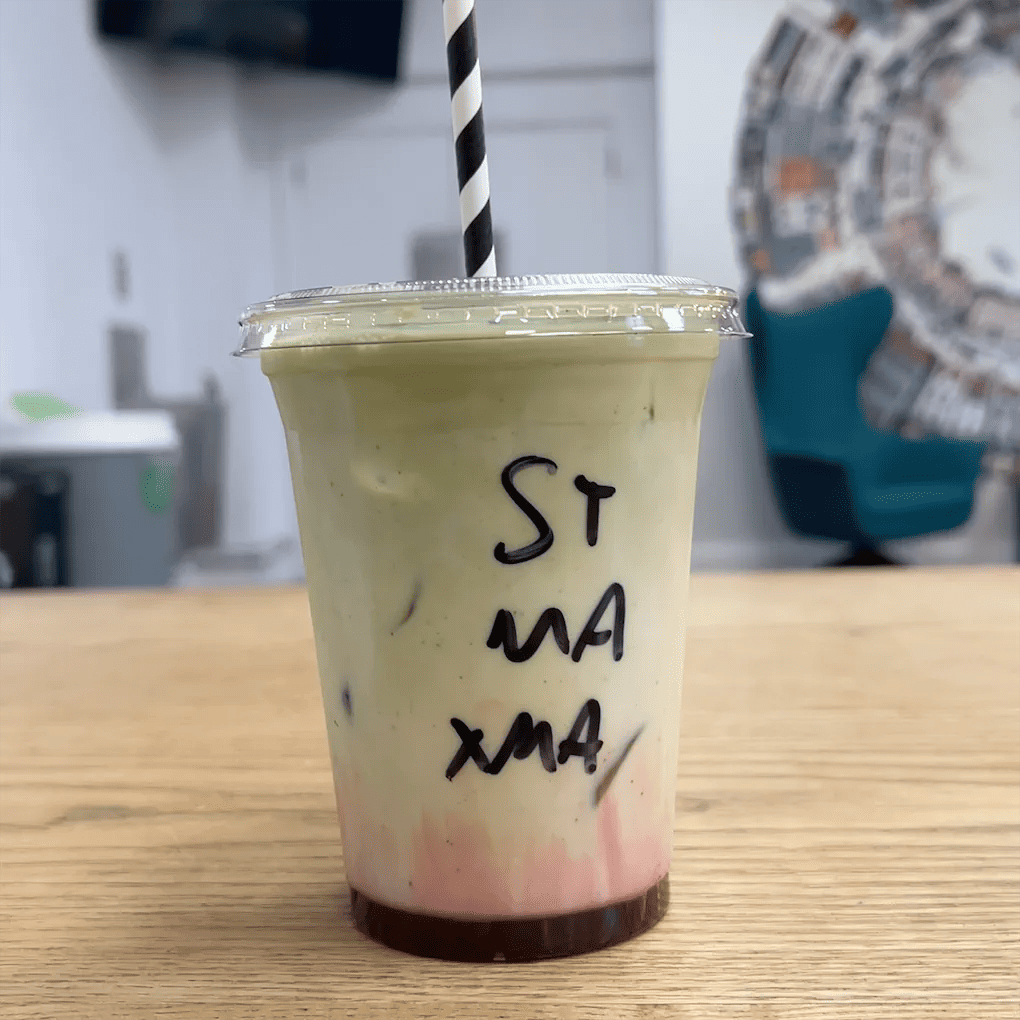
ファウンデーションコースの授業内容と評価方法
私はメディアについて勉強したかったので、 GoldsmithsのInternational Foundation Certificate in Media, Culture & Societyを選びました。
授業は週3日で、1日に2コマ(1コマ約1時間半)あることが多かったです。
カリキュラムは3学期制です。秋から冬までの1学期は専門分野の授業と英語の授業を受けます。冬休み明けからイースター休みまでの2学期も同じような形で授業が続きます。
3学期は復習期間で、毎週授業があるわけではないです。3回ほどの復習授業があるほか、主に最後の試験に向けて自分で勉強するスタイルでした。
専門分野の授業
ファウンデーションコースは大学での学びに備えるための準備コースであり、進学後を見据えた専門的な授業を受けられるのも魅力の一つです。
専門分野の授業では、1コマ目に大学1年次のlecture(講義)を受けます。続く2コマ目にファウンデーションコースの学生向けseminar(セミナー)が行われます。セミナーでは、先生が講義内容をわかりやすく解説してくれます。
初めて講義を受けたときは、教授の話がほとんど理解できず、正直かなり焦りました。その後のセミナーは留学生向けに行われるため、先生が簡単な英単語を使って丁寧に説明してくれたので、ほっとしたのを覚えています。
セミナーは解説を聞くだけでなく、discussion(ディスカッション)が中心です。クラスメイトは同じ学科の学生たちで、人数が少なく、アットホームな雰囲気があります。最初は緊張しながらも発言しやすかったです。専門知識の理解だけでなくスピーキング力も自然と伸ばすことができました。
評価方法
基本的に学期ごとに出されるエッセイで行われます。トピックや文字数は授業や先生によってまちまちです。ファウンデーションコースの学生にはtutor(チューター)と呼ばれる担当教員が付いていて、エッセイのテーマ決めから構成、内容まで相談することができます。チューターと一緒にプランを立てたあと、自分でエッセイを書き上げて提出します。
英語の授業(Reading/Writing/Speaking)
ここでは、アカデミックな英語力を身につけるために、Reading, Writing, Speaking(リーディング、ライティング、スピーキング)の3つのスキルに分かれて授業が行われました。リスニングに関しては、授業全体が英語で行われるため、リスニング専用の授業はありませんでした。専門分野の授業と異なり、ここでは他の学部を目指している学生たちと一緒に学びました。
ここからは、スキルごとにどのような内容の授業があったのかをご紹介していきます。
Reading
リーディングの授業は、1学期と2学期を通して行われました。初回の授業で、リーディングの問題がたくさん載っている冊子が配られました。そこには1週間ごとに課題が設定されており、順番に解いていく形式で進められました。
宿題は、例えば次の週がWeek 3の場合、「Week 3」と書かれた長文を読み、それに付随する設問をできるだけ自力で解いてくる、という感じでした。そして授業で答え合わせをしながら、内容に関連したディスカッションをします。
評価方法
学期末には、それまで取り組んできたのと似た問題が出題され、時間内に長文を読んで設問に答える形式のテストが行われました。
時間制限がある中で集中して解くプレッシャーもあり、特に最初のテストは思うように力を発揮できなかった記憶があります。それでも回を重ねるにつれ、読み取りのスピードや精度が上がっていくのを実感できました。
Writing
リーディングの授業と同様に、ライティングの授業も1学期と2学期を通して行われました。
1学期は、基本的なエッセイの構成方法について学びました。具体的には、thesis statement(主張文)の書き方、conclusion(結論)のまとめ方、reference(参考文献の記載)の方法など、アカデミックライティングの基礎を一つひとつ丁寧に学びました。
2学期には、週ごとに構成や段落、リサーチを積み重ねながら、1本のエッセイを完成させていきました。
評価方法
2学期に提出したエッセイが評価されました。評価のポイントは、文法の正確さ、アカデミックな語彙の使い方、そしてreferenceの形式が正確かどうかなどです。授業で学んできたことを総合的に活かす機会になりました。
Speaking
1学期はプレゼンテーション、2学期はディスカッションに向けて、スピーキング力を伸ばしました。この授業では毎回出されたトピックについてクラス内でディスカッションを行います。その中でプレゼンテーションのコツや、ディスカッションで使えるフレーズなどを習得しました。
クラスメイトとのディスカッションを通して、英語で意見を述べることにも少しずつ慣れていき、話すことへの抵抗がだんだんと減っていきました。
評価方法
1学期のテストでは、プレゼンテーションを行いました。与えられたトピックに対して自分でリサーチし、引用を交えながらPowerPointを作成して、クラス内で発表しました。
2学期のテストでは、4人1組のグループでディスカッションを行いました。トピックは1週間前に発表されます。それに関連する情報を自分たちで調べて、当日のディスカッションで意見を述べました。グループディスカッションでは、他の人の意見に応じて柔軟に会話を展開する力も問われ、とても良い実践の場となりました。
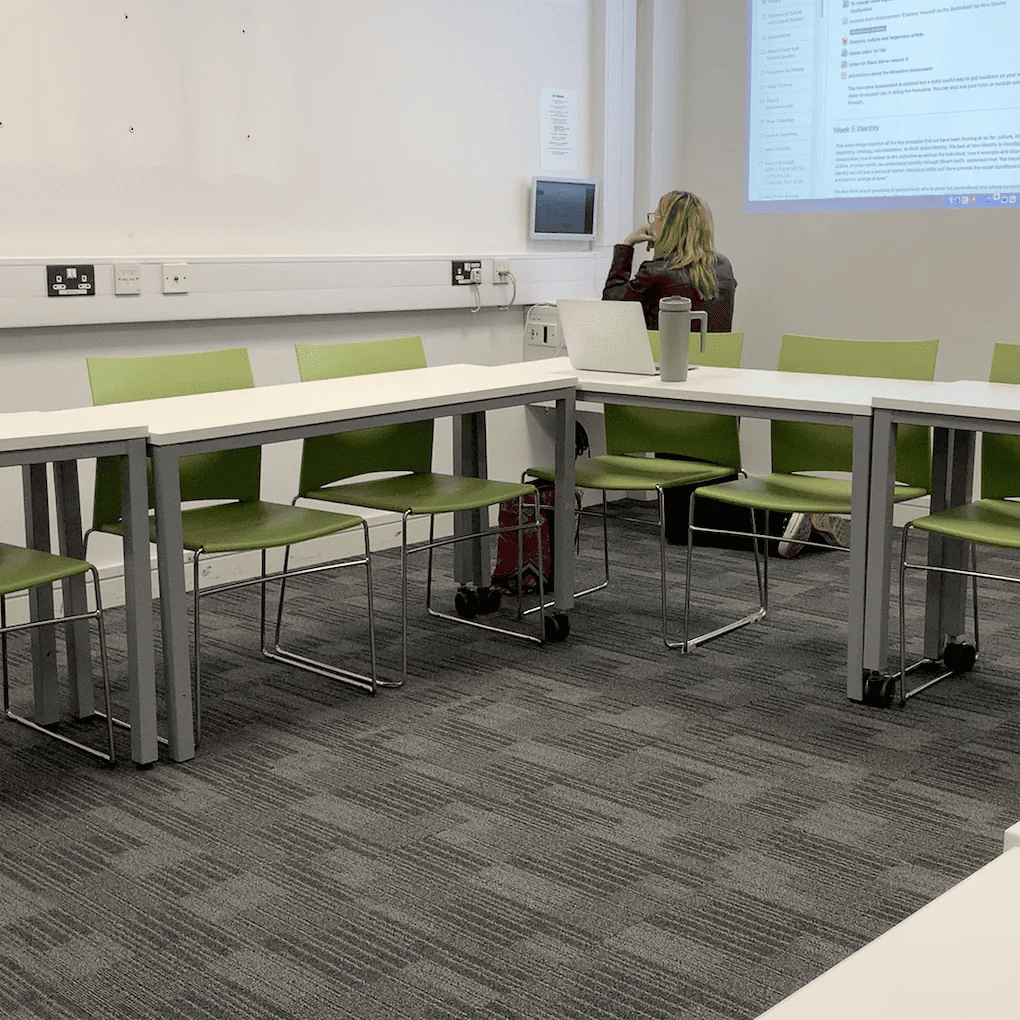
授業の雰囲気
大学1年生と一緒に受ける講義を除けば、ほとんどの授業は15人未満のクラスで行われました。最初は緊張しましたが、発言や質問がしやすい雰囲気で、自然とクラスになじむことができました。授業はキャンパス内の教室で行われ、毎週同じ教室を使っていたので安心感がありました。
先生方のスタイルは人それぞれですが、基本的にはフレンドリーで話しかけやすいです。また、わからないことも気軽に質問できました。日本と違って、授業の途中で抜けたり、お菓子を食べていたりしても注意されないなど、かなり自由な雰囲気でした。ただし、中には食べ物の匂いが気になるから教室内での飲食はやめてくださいと言う先生もいて、先生によってルールや雰囲気に違いがあると感じました。
クラスメイトの雰囲気
クラスメイトの国籍や雰囲気は、大学、進学予定の学部によって大きく異なると思います。私が受講したコースではアジア系の学生が多く、特に中国人が大半を占めていました。日本人は私を含めて4人だけで、少数のヨーロッパ系の留学生もいました。
さまざまなバックグラウンドを持つ学生たちと一緒に学ぶことで、日常の会話だけでも刺激がありました。最初は緊張しましたが、少人数ということもあって自然と会話が生まれます。友達もできて、ペアワークやグループディスカッションの時間が楽しみになっていきました。
ひとつ驚いたのは、学生たちがかなりゆるいことです。時間ぴったりに授業が始まることはほとんどありませんでした。先生が来るのも生徒が集まるのも開始時間の10分後くらい、ということが多かったです。欠席者もわりといて、日本との違いを感じました。カルチャーショックというよりは、むしろ面白いなと思いました。
受講後に感じた効果と学部進学
英語はどれくらい伸びたの?
ファウンデーションコースを始める前に受けたIELTSはOverall 5.5でした。それ以降はIELTSを受けていないため、数字で比較することはできません。しかし英語力は着実に伸びたと感じています。特に、英文を読むスピードが上がったと実感しています。スピーキングでも自分の考えを何とか英語で伝えられるようになりました。
中でもライティングの成長は大きいと感じました。コースを受講する前までは、英検で出題されるような短いエッセイを書くのが精一杯でした。当然引用の方法などは全くわかりませんでした。このコースを通して、エッセイの構成や書き方、参考文献の引用方法など、アカデミックライティングの基礎をしっかり身につけることができました。
正直に言うと、1年間で英語がペラペラになるのは簡単ではありませんでした。それでも英語を話すこと、そして失敗を恐れずにコミュニケーションがとれるようになったことは、自分にとって大きな成長だったと感じています。
ファウンデーションから大学1年生への進み方
私が通っていたファウンデーションコースでは、1・2・3学期に行われるテストでそれぞれ合格点を取ることができれば、そのままGoldsmithsの学士課程に進学できる仕組みでした。
そのため、普段の授業にきちんと出席し、課題やテストに真面目に取り組んでいれば、進級できないということはあまりないと思います。実際、私のクラスメイトの中で進学できなかった人は一人もいませんでした。ですので、過度に心配する必要はないと思います。
すべての試験に合格したあと、大学側から進学の手続きに関する案内メールが届きました。それに従って準備を進め、私も無事に大学1年生としての学びをスタートしました。
なお、ファウンデーションコースを修了したからといって、必ずしも同じ大学(私の場合はGoldsmiths)にしか進学できないわけではありません。成績次第では他大学への出願も可能な場合があります。 私の友人の中には、他大学への進学を希望して出願していた人もいました。その場合の出願手続きは先生がサポートしてくれるようです。ただ、保証があるのはGoldsmithsの学部であるため、私は迷わずそのまま進学しました。
ファウンデーションコースはイギリス大学留学の自信に繋がる
1年間のファウンデーションコースは、大学進学の準備だけではないのです。英語力の向上や、異文化の中での生活力を身につける貴重な経験になりました。最初は不安もありましたが、授業を通して少しずつ自信を持てるようになりました。そして大学1年生としてのスタートラインに立てたことをとても嬉しく思います。
これからイギリスでの進学を考えている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。興味のある方はぜひ、Goldsmithsのファウンデーションコースを検討してみてくださいね!