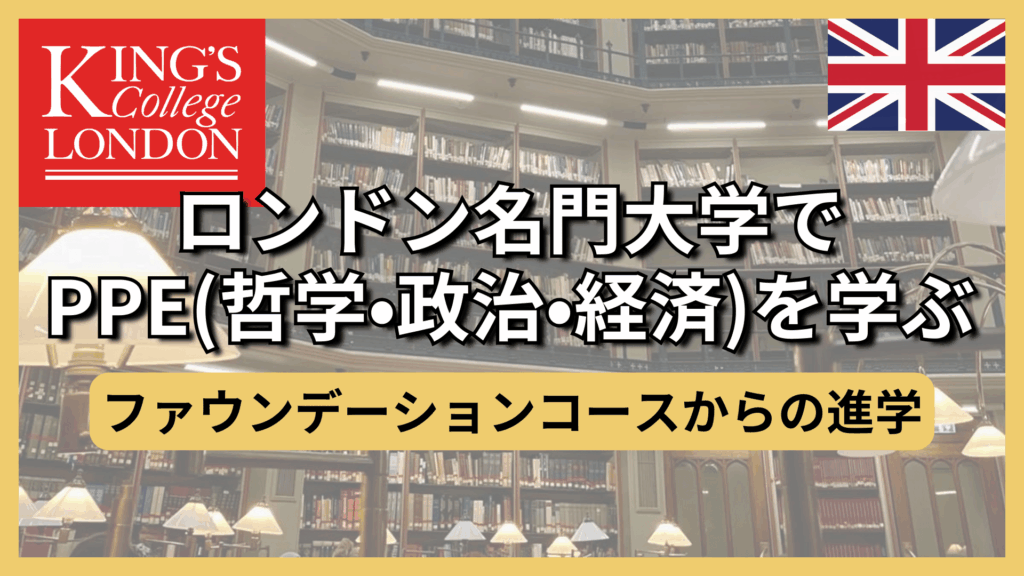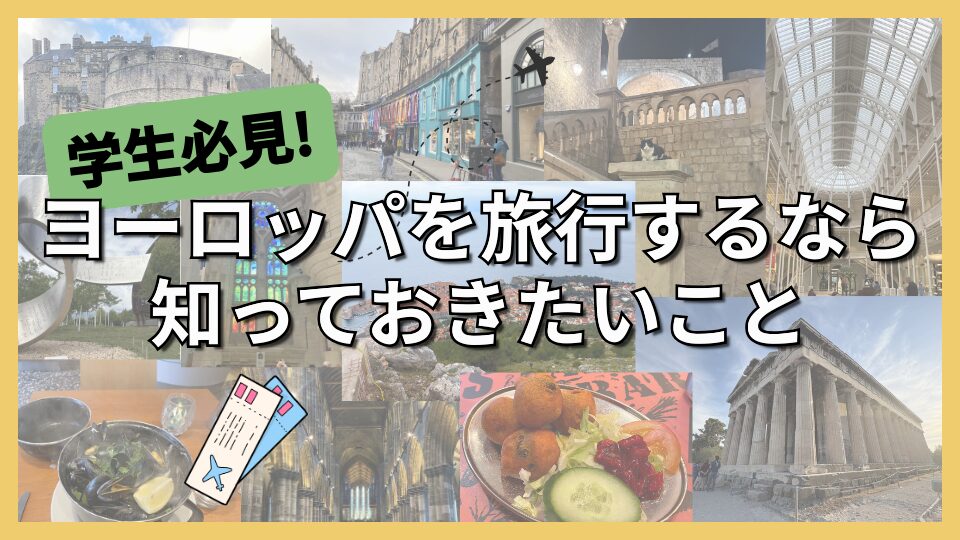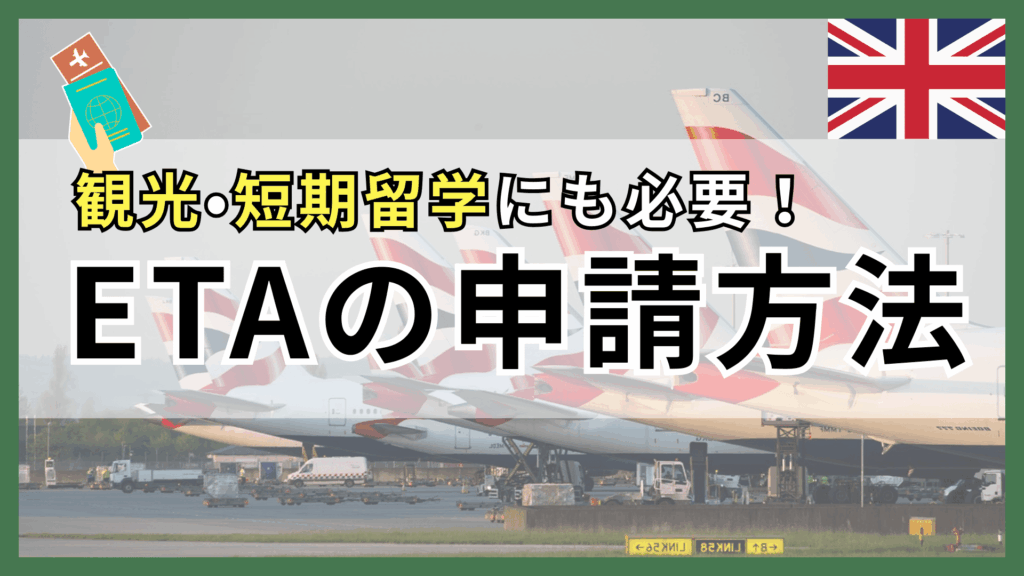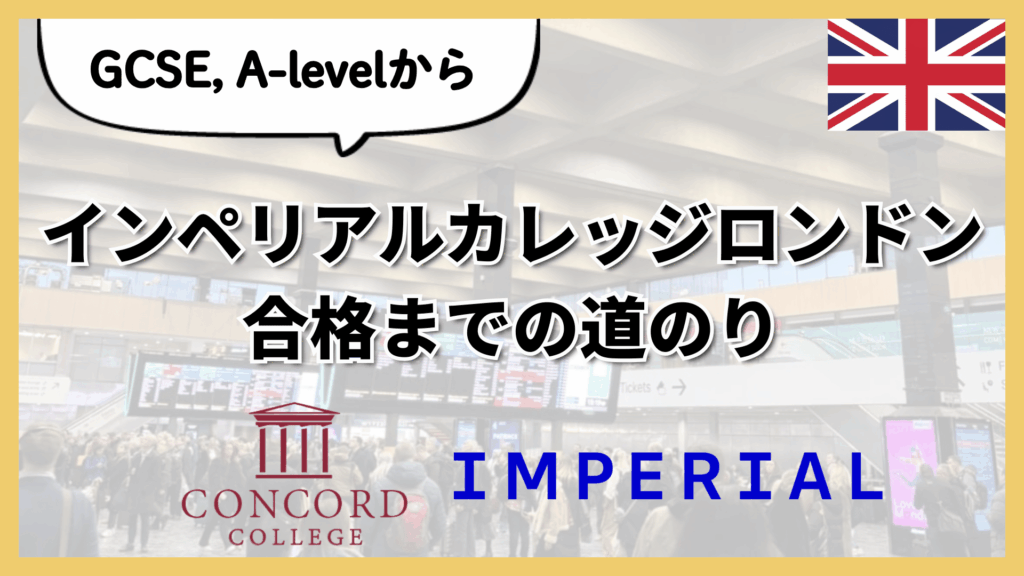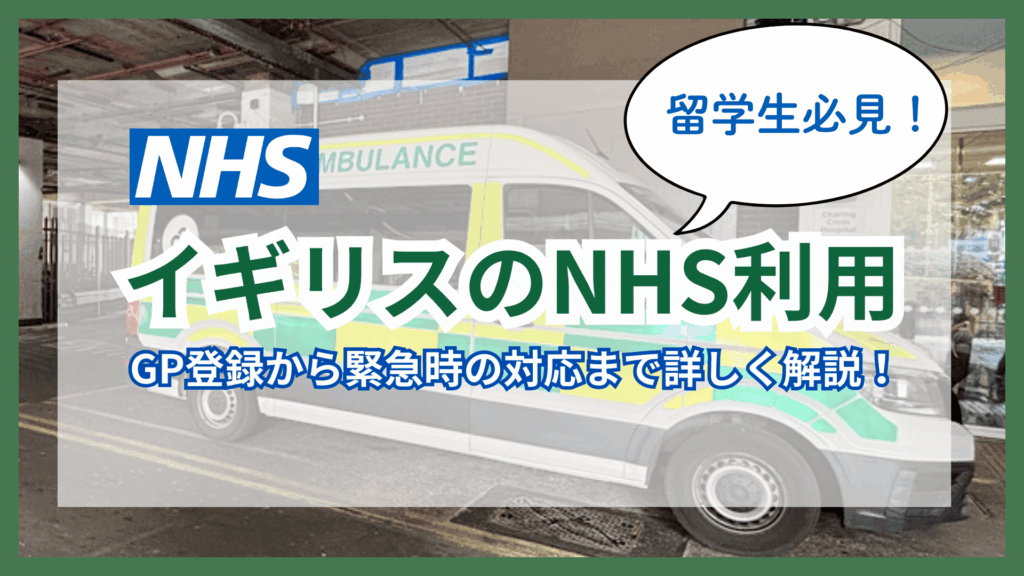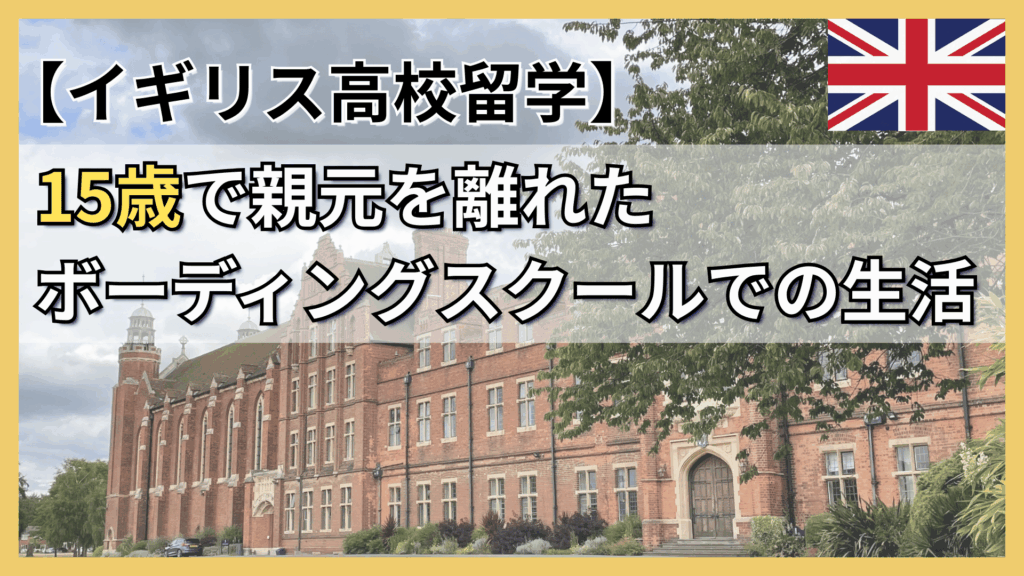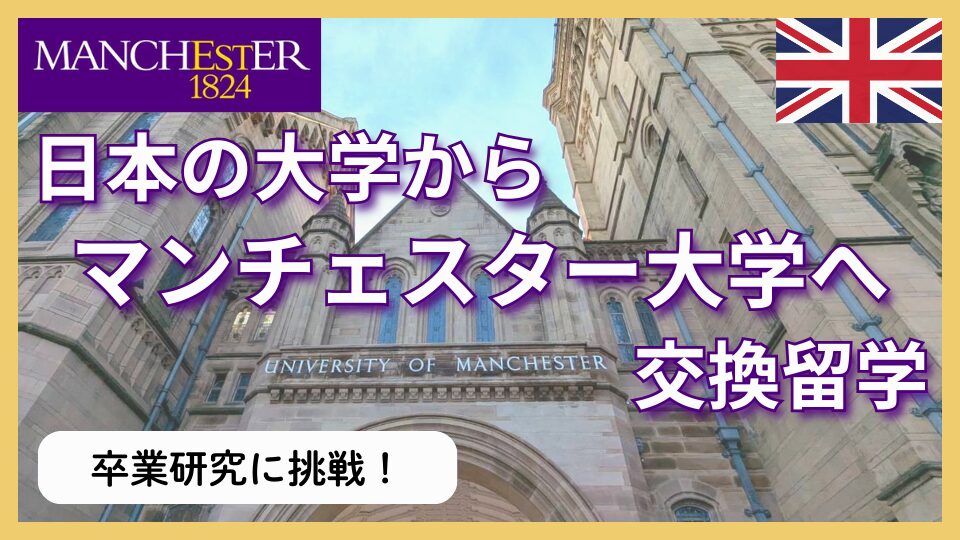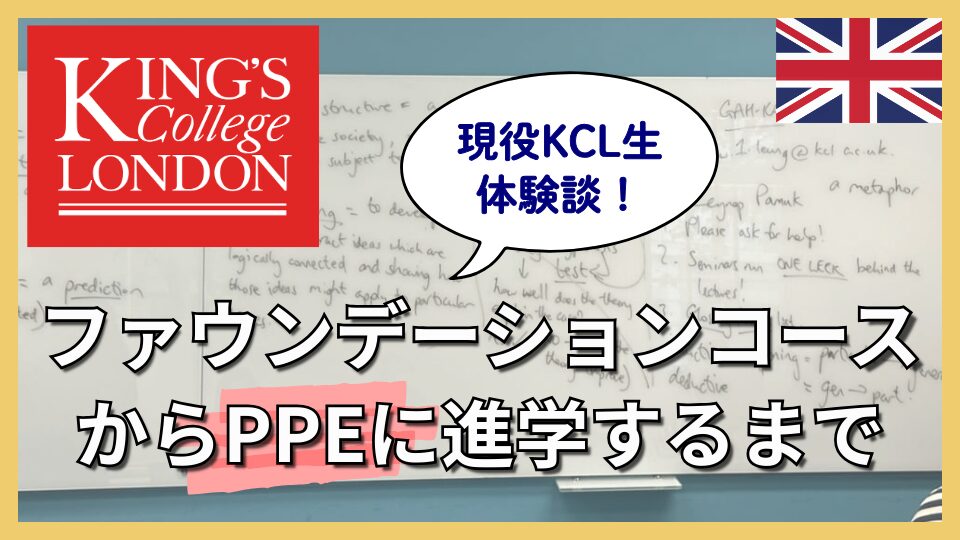Ryotaroさん
⽇本の公⽴⼩学校を卒業後、イギリスのボーディングスクール(全寮制学校)で7年間学び、その後The University of Manchester(マンチェスター⼤学/ UoM)に進学。ポルトガル語とビジネスマネジメントをダブル専攻し⽇本⼈会の会⻑を務める傍ら、パーカーブランドを運営。ラグビーに夢中。
マンチェスター大学: ポルトガル語とビジネスマネジメント専攻
専攻について教えてください。
マンチェスター⼤学のSchool of Arts, Languages and Culturesに所属しており、Portuguese and Business Management(ポルトガル語とビジネスマネジメント)の2つを専攻しています。
ポルトガル語は語学としての4技能を習得しながら⽂化⾯や歴史⾯の内容も学びます。この専攻の⼈数は学年で15⼈ほどと少ないため、lecture(講義)は会話教室のようなアットホームな環境で先⽣や学⽣同⼠の対話が活発に⾏われます。当然、どの授業に⾏っても同じメンバーと会うため、全員顔⾒知りで仲が良いです。3年次になると専攻している⾔語が話される国で1年間の交換留学に⾏きます。私はブラジルのサンパウロ⼤学に留学します。
ビジネスマネジメントでは、選べる講義の内容はさまざまです。私はマーケティング理論の基礎、国別の資本主義やその歴史などを履修しました。こちらはポルトガル語の授業とは異なり講義となると100⼈規模で⾏われます。講義のほか、seminar(セミナー)があり、その週の講義内容に関連したものを実践します。例えば講義で経済情報がまとめてあるグラフが出され、読解⽅法を教わったらセミナーでは作り⽅を学び、実際に⼿を動かします。授業の数は多くありませんが、テスト期間が近くなるとリーディングの課題が増えます。内容をしっかり読んで、関連の⽂献を調べながら理解を深めます。

その専攻を選んだきっかけは何ですか?
ポルトガル語を専攻したのはイギリスで通っていたボーディングスクールの環境が⼤きく影響しています。そこは50カ国以上から⽣徒が集まるグローバルな校⾵で、周りは常にさまざまな⾔語が⾶び交っていました。私は16歳の時にスペイン語を学び始め、スペイン語が話せる友⼈と⽇常的に会話していたことでかなりのスピードで上達しました。その成功体験から、⼤学でも⾔語を学びたく、南⽶で主要なポルトガル語を選びました。
ビジネスに関しては、⾃分たちで何かを作り上げて、それをお⾦に変えられるところが⾯⽩いと思っています。
実は中学⽣の頃、学校に置いてあった無料のオレンジを搾ってジュースにして寮の部屋まで配達するというサービスを思いつき、1杯0.5ポンドで販売したことがありました。インスタで宣伝すると毎⽇のようにオーダーが⼊り、この無謀なビジネスは思いのほか⼤繁盛しました。しかしオレンジの減り具合が激しくて学校側にバレてしまいました。2週間で私の初めてのビジネスは幕を閉じましたが、その過程はとても⾯⽩く、有益でした。
また、⾼3の秋には卒業⽣の起業した話など、キャリアについての講演を聴きました。それをきっかけに卒業生とつながり、2カ⽉間メキシコとコロンビアで⽣活も共にするインターンをする機会に恵まれました。起業している⽅々の活動を肌で感じ、彼らの⾏動⼒やメンタリティー、情熱に魅了さました。このインターンの経験が更なるビジネスへの興味につながりました。
ポルトガル語とビジネスマネジメントを1年半以上学んで、どうですか?
この2つの組み合わせを選んだのは最⾼の決断です。ポルトガル語は⽇に⽇に上達を感じます。新しい単語や表現を学び、頑張れば結果が出るのでやりがいを感じます。ポルトガル語に加え語学と同じくらい関⼼があり、かつ語学と全く違う分野であるビジネスを勉強することでバランスが取れていると思います。これよりいいチョイスはないと⾔えるくらいすごく楽しいです。
「みんなを笑顔にしたい」日本人会の会長として
Manchester Japan Society(日本人会)の会長を務めていると聞きました。
昨年度会⻑職に⽴候補し、当時の執⾏部による⾯接などを経て選んでいただきました。僕は11歳からイギリスの全寮制学校に⼊り⽇本⼈は数⼈しかいなかったです。そのため、必然的に⾃分はある種その場の「⽇本代表」として⽇本のイメージを背負っているといったnational identity(国民意識)がありました。そのため、「⽇本のために何かをやりたい」と常に思いながら⽣活していました。この思いは⼤学に⼊ってからも続いていて、⽇本⼈会の会⻑になれば⽇本のためにできることの幅が広がると思いました。

会長として、どういう方針で会を運営していますか?
会としての仕事をしっかりやるプロフェッショナルな⾯はもちろんですが、「楽しくないといけない」と思っています。笑顔を絶やさず、元気で楽しい会にするのがモットーです。会⻑の雰囲気が組織の空気を⼤きく左右するので、⾃分が先頭に⽴って笑顔で、楽しく取り組むことを⼼がけています。
Ryotaroさんが会長になってから始めた取り組みはありますか?
⾃分の代になってからいつくか変更したことがあります。 定期的に⾏われている「パブソーシャル」という皆がパブに集まって飲みながら交流するイベントがあります。昨年まではただ場所を提供しているだけでしたが、今年からはビンゴ⼤会や変顔⼤会などのミニゲームを追加し、飽きずに参加してもらえるようにしました。
また、イベントのクオリティを上げるため、会員制を導⼊し、年間7ポンドの会費を徴収しています。
もう1つ⼤きなイベントとしてロンドンで開催された⽇本⼈のボートパーティに初めて参加したことです。イギリスの13の⼤学にいる⽇本⼈学⽣約700⼈が集まり、UoMからも25⼈が参加しました。他⼤学にいる⽇本⼈と交流できた実りのある会だったので来年につなげていきたいです。
マンチェスター大学でのビジネスチャンス
課外活動は日本人会以外に何かしていますか?
授業で習ったこともそうなんですが、インターンの経験を何かに⽣かしたいと思い、昨年夏に「Manny Bees」というパーカーのブランドを⽴ち上げました。 UoMの公式グッズはいろいろありますが、あまりクオリティが良くないと感じております。値段か⾼い割にそれほどかわいくない点にも注⽬し、それなら⾃分で作ろうということで始めました。
友達に助けてもらいながら、Student Union(学⽣会館)のフリースペースで試験的に展⽰販売をしたり、インスタに投稿する宣伝⽤の写真の撮影会を開いたりしてすごく楽しいです。これをマンチェスターの思い出の⼀つとして⼿に取ってほしいので、クオリティが良くて、かわいくて、低価格にできたものを提供したいと思っています。

大学に入ってからもインターンしていますか?
はい、⻑期休暇にインターンします。昨年はドイツのミュンヘンのオークションハウスに⾏きました。出品者から物を預かって、それをオークションで売ります。先ほど⾔ったコロンビアとメキシコでのインターンは今も続けています。例えばソフトウェアの新サービスのピッチプレゼンテーションを⽇本の⻁ノ⾨ヒルズやスペインのビルバオで行うなどをしました。このようにマーケティング関連のことを主にしています。
ケガをしても冷めないラグビーへの愛
スポーツは何かやっていますか?
⼩1からサッカーを始め、中3にラグビーに転向し、それからずっとラグビーをやっています。しかし2年前の夏、プレイ中に転倒し膝の前⼗字靭帯を痛めてしまいました。そこからは体を動かす程度です。本来は⼿術をして治すべきですが、術後のリハビリを考えると留学に影響が出てしまうため今は諦めています。そう⾔いつつもたまに我慢できずラグビーをしてしまいます。

マンチェスター大学留学生活: 日常の幸せ
現在は寮に暮らしていますか?
初年度は学⽣寮に暮らしていました。2年⽣になってからは⼤学より南のエリアで友達3⼈と⼀緒にシェアハウスしています。⼤学からやや遠くバスで20分かかり、毎⽇満員バスに乗ってキャンパスを往復しています。
このエリアはナイトライフが活発で、夜は結構騒がしく⽇本⼈学⽣からあまり好かれないエリアかもしれないです。⽂化的に合っていないというか。ただ、私は⼈と交流したり友達とパブに⾏ったりするのが好きなのでこのエリアは⾃分に適していると感じています。
シェアハウス生活はどうですか?
すごく楽しいです。ハウスメートたちとは仲も良くトラブルもありません。これ以上良いハウスメートはいないんじゃないかと思うくらいです。
また、スーパーが近いというロケーションもすごく重要です。シェアハウスをすると話し合った時にスーパーから近いところにしようと決めました。夜、急にチョコチップアイスを⾷べたくなった時にすぐに買いに⾏けるんですよ。この利便性は本当に⼤事ですね。家でラグビーの試合を⾒ている時なんかは、ハーフタイムにダッシュで買いに⾏っても後半戦に間に合うんです。
食事はどうしていますか?ハウスメートと一緒に作りますか?それとも各自ですか?
たまに⼀緒に作って⾷べることもあるんですが、基本的には各⾃で作りますね。⾷べたいものが全然違うので。僕はスパゲティを作ることが多いです。安くて簡単で速い、⼤学⽣に必要な三要素がそろっています。そしてビタミン不⾜には気をつけるようにしています。
マンチェスターは学生が住みやすい街
マンチェスターに2年間暮らしてみて、どうですか?
とても住みやすい街だと思います。マンチェスターはシティセンターの端から端まで歩いて30分しかかからないです。⾏きたいは基本的に徒歩範囲内です。加えて、バスが24時間⾛っているのがありがたいです。
街と⼤学が⼀体になっているところも住みやすいと感じる理由です。ロンドンの⼤学だとキャンパスが街の中⼼から離れているところが多いのですが、マンチェスター⼤学はキャンパスの周りにいろいろな店や施設がそろっているので便利です。
日本の公立小学校を経てイギリスへ留学
11歳に渡英したとのことですが、どういう経緯でイギリスに来ることになったのですか?
イギリスに⾏こうと思ったのは⼤きく2つの理由があります。1つは当時サッカーをしていて、海外のレベルで挑戦してみたかったからです。もう1つはハリウッド映画にすごくハマっていて、英語への憧れがあったからです。
⼤⼈になるとアイデアが浮かんでもあれこれ考えてしまうと思うのですが、当時⼩学⽣の私は「サッカーがしたい」「英語がしゃべりたい」という2つの原動⼒だけで両親に相談したら背中を押してくれました。イギリス南東部の中⾼⼀貫のボーディングスクールに⼊学し留学⽣活が始まりました。両親は⽇本に残り、単⾝で渡英して今に⾄ります。振り返ると当時はよくやったなと思います。
最初の1年間はとにかく何をやっても⼤変でした。⾔葉が通じなくて、指⽰が理解できず何をすればいいか分からなかったです。授業にもついていけなかったです。意味が分からないことで怒られたこともありました。

英語があまり話せなかったということで配慮してもらいましたか?
僕は11歳で⼊学しましたが、この年齢で英語ができないという⼦がそれほど多くなかったので特別扱いはなかったです。そういう体制が整っていなかったと言ったほうが正確かもしれません。⾼校⽣の学年になると留学⽣も増えるので英語の補習クラスなどがありました。ですが、私の⼊学した年齢ではそれがなかったので、英語の海に投げ込まれた感じです。今考えるとそれが良かったですね。最初からネイティブと⼀緒に授業を受けたので、現地の⼦たちとの関わり⽅が早いうちに分かり、彼らに溶け込むのが⽐較的スムーズでした。
つらいことだらけだった生活をどうやって乗り越えたんですか?
気合ですね。本当は諦めることもできました。両親に「もう無理」と⾔えばやめることができたと思います。でも自分としては諦めるという選択肢はなくて、何が何でもやり切りたかったです。我慢と忍耐⼒で乗り越えた当時の経験が今の私の礎になっています。
留学生活に慣れるまでどれくらいかかりましたか?
1年もかからないうちに慣れました。英語⼒に関しては、1年⽬は⾃分の気持ちを少し伝えられて、2年⽬は相⼿の話を聞いてしっかり受け答えができるようになりました。3年⽬になると思い通りに会話ができました。このように成⻑していることを⾃分でも段階的に実感しました。3年⽬が終わる頃にはいわゆる“英語ペラペラ”になっていたと思います。
その時点で英語が話したいという目標はクリアしたということですね。
はい、確かに英語が学びたいという1つの⽬的は達成しました。しかし私にとって英語は⽬標ではなく1つのスキルです。⽬標を達成したというよりはある1つのスキルを⼿に⼊れたと捉えています。
なるほど、ではもう1つの目的だったサッカーはどうなりましたか?
僕が⼊った学校にはChelsea Foundation(チェルシーファンデーション)がありました。Chelseaはイギリスプレミアリーグのサッカーチームで、そのアカデミーファンデーションに加⼊しました。このクラブがあったことが⼊る学校を選んだ理由の1つです。
でもラグビーをやってみて分かったのですが、⾃分のサッカーへの愛というか、情熱はラグビーに⽐べると全然⾼くなかったです。ラグビーの魅⼒には⼀試合で染まりました。今は「ラグビー⼤好き!」です。
ラグビーが好きになったのは試合を観戦したのがきっかけということですね。
いえ、16歳の時、他校との試合に「1⼈助っ⼈が欲しい」と⾔われたことが始まりです。「じゃあ俺がやるよ」と、タックルの仕⽅すら分からないのに出場しました。
初戦で相⼿のデッカい選⼿がボールを持ってこっちに向かってきました。私の後ろがタッチラインだったので抜かれたらアウトになってしまうと思い、必死に守ろうとしました。アタックのやり⽅が分からないのでその選⼿に抱きつき、どうにかして⽌めようとしました。だが次の瞬間、相⼿の肘がバーンと顔を直撃し、⿐が折れてしまいました。結局トライを決められ、「俺の⿐⾎はなんだったんだ」となりましたが……。
それでも、ラグビーのメンタリティーや団結感がすごく好きになりタックルも楽しいなと思い、サッカーを置き去りにしてラグビーに転向してしました。
普通はトラウマになると思うのですが、すごいですね。
それは両親と家族のお陰だと思います。
実はラグビーで前⻭が1回折れかけたことがあります。普通の親御さんですと動じて「そんなスポーツやめなさい」などと⽌めるのではないかと思うのですが、私の⺟は「しっかりやりなさいよ」と。こんな感じで、⼤変なこともサポーティブに前向きにしてくれたことでトラウマにもならずに続けることができています。また、そういう姿勢は海外⽣活する上での助けになっています。
海外大学生の就職: 日本の企業に就職したい
卒業後はどういう予定ですか?
⽇本の企業で働きたいです。
海外で勉強した学⽣は結構外資系企業に就職する⽅が多いと思います。でも私は⽇本⼈⼀⼈⼀⼈が⾃信を持ち、世界で戦うリーダーや組織の成功例を増やしていきたいからこそ、⽇本企業にこだわります。その理由は⽇本⼈の団結⼒というものはすごく強いと感じているからです。
例えばサッカーを⾒ても、ブラジルとの試合では、選⼿⼀⼈⼀⼈のレベルは圧倒的にブラジル⼈のほうが⾼いですが、最後は⽇本が勝ちます。なぜかというと団結⼒という⽇本の素晴らしさがあるからです。これはビジネスでも共通するところがあると考えています。⽇本企業で同じ⽬標に向かって団結すれば⼤きなものを⽣み出していけると思います。